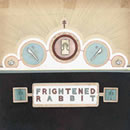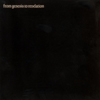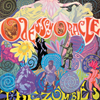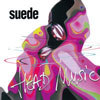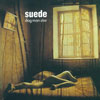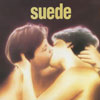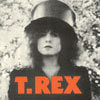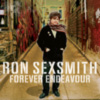フライトゥンド・ラビット、スコット大いに語る!
いよいよ4月21日に発売となる ニュー・アルバム『The Winter Of Mixed Drinks』について、スコット・ハチスン(Vo、G)の最新インタビューをお届けします。

 ——フライトゥンド・ラビット(=おびえたウサギ)とはユニークなバンド名ですが、まずはその由来をうかがえますか?
フライトゥンド・ラビットは、小さいころ、親から付けられたあだ名なんだ。子供のころ、僕はとてもシャイでね。まわりの子が怖くて、いつもひとりで部屋の隅に座っているような子どもだった。ほかの子たちとしゃべるのにも苦労していたよ。5歳ぐらいまでのことだけどね。というわけで、バンド名は僕の子供のころのニックネームに由来するんだ
——フライトゥンド・ラビット(=おびえたウサギ)とはユニークなバンド名ですが、まずはその由来をうかがえますか?
フライトゥンド・ラビットは、小さいころ、親から付けられたあだ名なんだ。子供のころ、僕はとてもシャイでね。まわりの子が怖くて、いつもひとりで部屋の隅に座っているような子どもだった。ほかの子たちとしゃべるのにも苦労していたよ。5歳ぐらいまでのことだけどね。というわけで、バンド名は僕の子供のころのニックネームに由来するんだ——当時は、文字どおりウサギのように、ちょっとしたことにおどおどしていたんですか? そうだよ。ちょっとしたことにビクビクしていた(笑)。今でもたまに、そういうことがあるよ。昔ほどじゃないけどね
——たとえば、キレイな女性の前とかで? それはもちろんじゃないか! 男はみんな、そうなんじゃないかな(笑)
——そのフライトゥンド・ラビットですが、現在のようなバンド形態ではなく、最初はスコットのソロプロジェクトとして2003年にスタートしたそうですね。当時、ステージで自己紹介をすると、観客はどんな反応をしました? 今でもバンド名を紹介すると、おもしろがられたり、笑いが起きたりするよ。ヘンな名前だと思われるんだろうね。でも、大観衆ではないにしろ、ライヴ会場にいる大勢の人たちの前で、自分が内気だということに由来するフライトゥンド・ラビットを名乗ってプレイをするなんて、おかしなもんだよね。自分でも、こういう仕事をすることになるなんて思っていなかったから、ステージで自己紹介するときは、自分でも楽しんでいた。それに、人前でライヴをするのを怖いと思ったことは一度もないんだ。不思議だよね。間違いなく、僕はステージ用の人格を持っていると思う。これは、実際の自分とはかなり違うものだ。ライヴのときは自信があるんだけど、普段はがんばらないとしゃべれない。このステージネームは、そんな僕をちょっと手助けしてくれていたのかもしれないな
——メンバー4人で制作した2作目の『THE MIDNIGHT ORGAN FIGHT』(2008年)が大ヒットし、一昨年から去年にかけてはツアー三昧でしたね。驚きや楽しさが多い反面、肉体的にも精神的にもかなり疲弊したのでは? 指摘のとおり、肉体的にも精神的にも疲れたよ。絶えず移動があって、ときには一ヵ所に30分もいられないことがあるんだから(笑)。でも、不満は言えない。そのおかげで世界各地に行けるからね。健康に良くないことは確かだし、こういう生活を長く続けていいとは思えないけど、ツアーはすごく楽しいからね
——この2作目の評価が非常に高かっただけに、3枚目となる新作へのプレッシャーは尋常ではなかったはずです。曲作りのためにスコットランド東部にあるクレイルという小さな町にひとりで赴いたそうですが、その最中もプレッシャーと闘っていたのですか、それとも制作に没頭できたのでしょうか? プレッシャーはもちろんあったし、むしろそれを意識するようにしていた。プレッシャーを成長するために使えば、バンドはいい方向に向かうんじゃないかな。みんなからいいレコードを期待されていると思えば、そのレベルに達することを目標にするようになる。プレッシャーによって仕事ができるし、生き生きと、活動的でいられる。だから、プレッシャーは重要なものだと思うんだ。創造性を抑制するものにはしちゃいけないけど、自分をがんばらせてくれるプレッシャーなら、僕は好きだよ。いい意味でのプレッシャーがね
——クレイルでは、電話もインターネットも使わないほど、自分を孤立させていたんですか? うん、インターネットはなかった。なにしろクレイルは人里離れたところで、携帯の電波もあまり届かないんだ。僕が住んでいた小さい家には電話が1台だけあり、その番号を知っていたのはガールフレンドのほか、2、3人のみだった。僕は慌ただしいこの世界から離れたかったし、そうすることでまた元気になりたかったんだ。あれは間違いなく、身を潜めて、自分がフライトゥンド・ラビットをやっている理由を再び見出すプロセスだった。クレイルへ行ったからこそ、またバンド活動をしたり、ツアーをするってことに対してわくわくできるようになったんだ。1ヵ月半ほどいたんだけど、それで十分だったね。そのくらい経つと、元気を取り戻し、また人と一緒にいたいと思うようになるものじゃないかな(笑)
——そのあいだは誰にも会わなかったと? 人と会うことはあったよ。やっぱり人と話をしたりするのって必要だろ? ずっと誰とも会わないということではなかったよ。ただ、これまでにないほど多くの時間をひとりで過ごしていたね
——ちなみに、クレイルであなたがひとりで曲作りをしているころ、ほかのメンバーはどこでなにをしていたのでしょう? 実はよく知らないんだ(笑)。みんな、グラスゴーに戻っていたんじゃないかな。長く付き合っていると、友だち同士でもギクシャクすることってあるだろ? 僕たちは長いこと4人で一緒に活動してきたから、それぞれ自分の時間を過ごしたくなったんだ。アンディ(・モナハン/b, key)は曲を作っていたと思うし、僕の弟のグラント(・ハチスン/ds)はビリー(・ケネディ/g)とちょっと仕事をしたり、多少はルーティーン的なことをやっていたかもしれないね
——曲作りの進行具合などについて、ときどきメンバーと電話で話したりは? 特に電話はなかったよ。僕の方から彼らに、たまにメールしていたからね。実は、できた曲を彼らにネット経由で送り、それを聴いた彼らからフィードバックをもらっていたんだ。ただ、僕はバンドのみんなからすごく距離をおきたかった。結局、メンバーと絶えずべったり一緒にいない方が、バンドとして曲もより多く作れるし、健全なんだと思うよ
——でも、インターネットがない場所にいたんですよね。メールを使う際には、ネットカフェのようなところへ足を運んでいたということですか? そうなんだ。16kmほど離れたところに町があって、そこまで出かけていって曲を送った。でも、たいていはCDに焼いて、メンバーに郵送していたんだ。僕は今でも結構、郵便を使うんだよね。途絶えかけているシステムではあるけど、僕はいまだに郵便が大好きなんだ
——さて、新作『THE WINTER OF MIXED DRINKS』には、海や波を彷彿とさせるメロディや歌詞が多いですが、あなたの育ったセルカークにも、バンドが活動の拠点にしているグラスゴーにも海はありません。やはり、海沿いの町クレイルで曲作りをした影響だと思われますか? 絶対そうだね。大きな影響を受けたよ。僕は海沿いに住んだことがなくて、ずっと海のそばに住んでみたいと思っていたんだ。だからクレイルでは毎日海まで散歩に出かけたし、そんなときにアイディアが湧いたものだよ。自分が想像していた以上に影響されたね。特に内陸部にしか住んだことがなかった、僕のような人間にとっては強烈だった。そこに存在する自然の力に圧倒されるし、海には人を癒すようなものがあるだろ? だからアルバム全体にわたって、大きな影響が出ているんじゃないかな
——クレイルで、すべての曲を書き上げたんでしょうか? ああ、ツアー中に曲作りをするのは好きじゃないんだ。ツアー中の曲作りは、すごく困難だってわかっているからね。だから、クレイルに行く前に作ろうとは思わなかった。それに、アルバムの曲作りは一気にすべてやってしまうのが好きなんだ。その方がアルバムが凝縮されて、すべてが密になるから。だから、クレイルに到着したときは、なにもない状態だった。新しいアルバム用の曲が書けるのか、最初は自分でも結構不安だったけど、まっさらなところから曲を作り上げていくのは、おもしろいプロセスだったよ
——実際に何曲書いたんですか? アルバムに収録されている曲以外に、さらに2曲ほどあったかな。だから12、13曲だね。僕はあまりたくさんの曲を書く方ではないんだ。数多く書くよりも、限られた曲をできるだけ濃く、いいものにしたくて
——前作や、特にデビュー作『SING THE GREYS』(2006年)が好きだったファンは、新作のスケール感に驚くはずです。古いファンにもなじみやすい“Nothing Like You”のようなパワフルな曲ではなく、あえて静かなイントロで始まり、洗練されたドラマティックな楽曲“Things”を1曲目に持ってきた理由は? 確かに、“Nothing Like You”のような曲は、ほとんどのファンにとって“Things”のような曲よりもずっと聴き慣れた感じがするだろうね。でも、僕は今回のアルバムをサプライズのあるものにしたかったんだ。あまり耳慣れないタイプの曲をアルバムのオープニングにもってくるのは、おもしろい試みだし、アルバム全体にこれまでとは違う光を当ててくれるんじゃないかと思ったんだ。“Nothing Like You”はフライトゥンド・ラビットのスタンダードな曲だよね。でも、“Things”にはもっと深みがあって、僕にとってはパーフェクトなオープニング曲なんだ。しかもこの曲は、新作のテーマをかなりよく打ち出しているし」
«前半より

——では、そのアルバムのテーマとは? 曲を書き始める前から、“Swim Until You Can't See Land”というキーワードがあったんだけど、実際にテーマになったのは、人生で必要ないものを大事にするのではなく、実際に必要なものにフォーカスしろっていうこと。自分を知ることから逃げるな、自分を作り上げているものを見つけろ、そんなことがテーマなっているんだ。だから、人生に実際には必要のない、ゴミのようなものを集めるのはやめろと歌っている“Things”が、アルバムのいいオープニングになると思った
——ストリングスを多用した曲を後半にもってきたりと、曲順にかなりこだわっているように思います。もしかして、アナログ盤のA面、B面を意識して曲を並べていますか? そのとおりだよ。僕はレコード育ちじゃないけれど、シングルのセレクションのようなものよりも、アルバム的な作りのCDを聴いて育った。だから始まりと終わりがあるような作品により惹かれるんだ。それぞれの楽曲がうまくつながるような曲順を決めるのに、僕たちはずいぶん時間をかけたよ。曲同士がなんの関連ももたないようでは意味がないから、アルバム全体がひとつの曲になるように考えたんだ。フォーマットとしても、僕はレコードの形が大好きだから、間違いなくアナログ盤の形式を受け継いでいるよ
——7曲目の“Man / Bag of Sand”は、2曲目“Swim Until You Can't See Land”のサビを反復した、リプライズのような曲です。インターミッションのようでもあるし、アルバムのいいアクセントになっていますが、この曲を作った意図は? 後半に向かうにあたり、みんなに出発点を再認識してほしいと思ったんだ。ここまできたけれど、まだこのテーマは存在しているんだよ、みたいな。テーマをバリエーションの形で再び提示したかったんだ。僕はいつも曲の一部を他の曲でも使うとか、曲の断片をあらゆるところへ入れるとか、そういったことをとおして全体をひとつにまとめるのに興味があるんだ。だから、テーマを繰り返し提示したり、多少の変化をつけて反復している。それに、タイトルにもなっている“Swim Until You Can't See Land”というフレーズは、さっきも言ったように、曲作りを始める前からあったキーワードだし、曲としてもインパクトがあった。実はこの曲は、クレイルですべて録音した楽曲で、どうしてもアルバムに入れたかったというのもあって。ほかの曲は、バンドのメンバーと一緒に別の場所でレコーディングしたんだけどさ。ただ、しばらくしてから振り返ってみたとき、海のそばで完成させたこの曲をアルバムに入れるのは、とても重要に思えたんだ
——曲を書くときは、歌詞と音楽のどちらが先に浮かぶのでしょうか? いつも音楽だね。たいてい部屋で腰をおろし、ハミングしながらとか、ナンセンスなことを適当に歌いながらギターでコードを弾いてみる。歌詞は後から付けるんだ。いつも音楽が先だよ。みんながすぐ歌えたり、記憶に残りやすいようなメロディやフックが大事だからそうしているんだ
——そういった曲作りの段階から、新作にチェロ、ヴァイオリンなどのストリングスを導入することを考えていたんですか? 考えていたよ。前からずっと入れたいと思っていたんだけど、これまでアレンジャーと一緒に仕事をする機会がなかった。今回はレーベルメイトであるハウシュカ(HAUSCHKA)を推薦され、ストリングスのアレンジを頼むことにしたんだけど、彼が本当にいい仕事をしてくれたんだ。それに、今回は以前よりもレコーディングに時間をかけられたから、自分たちにできることをすべてやりたかった。ああいう楽器を加えることは、僕たちにとって自然な成り行きだったよ。これまでチャレンジしたことがなかったからおもしろかったし、いい経験になったな
——新作収録曲が初めて頭に浮かんだとき、すでにヴァイオリンやチェロのサウンドをイメージしていました? ああ、イメージはすでにあったよ。曲を書き始めると、ごく初期の段階からでも、曲が勝手に頭の中で作り上げられていく。だから、今回のアルバムはとても映画的で、雄大な風景が浮かび上がるような作品になるって、最初からわかっていた。ストリングス、チェロ、ヴァイオリンなどの楽器は、なによりもそういう雰囲気を作る手助けをしてくれると思うんだ。僕はこれまで以上に、曲にそういったエモーショナルな側面を加えることに夢中になっていたよ
——自分が頭で思い描くとおりにストリングスのアレンジをするのは難しいと思いますが、どんなところに苦労しましたか? 手伝ってくれたハウシュカは、すごく腕利きのアレンジャーなんだ。彼はクラシック系のアーティストだけど、すごく実験的でもある。彼の力を借りたら、これまで僕たちだけではなし得なかったことができると思った。なにしろ僕は、これまでストリングスのアレンジをしたことがなったし、どこから始めたらいいのかもわからなかったから。最終的に彼は、僕がやりたかったことを現実のものにしてくれた。僕には思いつきもしなかったような要素も、たくさん加えてくれたんだ。彼とはとても実りの多い関係を築けたよ。彼はドイツ人で、ドイツ在住だから、僕たちは“これを外してくれないか”とか“これをやってみてほしい”といったことを、メールや電話でやり取りしながら、ストリングスの部分を一緒に作り上げていったんだ。彼は英語に堪能なんで、コミュニケーションを取るのにも問題はなかったし。彼のアイディアが僕らのものとは違っていることもあったけど、そんなの当たり前のことだし、だからこそ一緒に取り組んだわけだから、最終的にとても楽しかったよ。彼は本当にすごい人で、何年にもわたって音楽を作っており、とても経験豊かなんだ。直接会ったのは、一度だけなんだけどね
——そういったストリングスを含め、新作はこれまで以上にスタジオで作り込んだサウンドなので、ライヴですべて再現するのは容易ではないですよね。新メンバーのゴードン・スキーン(g,key)を新作完成後に迎え入れていますが、これは今後のツアーのことを考えた上での増員なのでは? そのとおりだよ。今回のアルバムはとても密度の濃いアルバムだから、僕たち4人ではライヴで十分に表現できないと思ったんだ。僕にとって大事なのは、ライヴでアルバムをそっくりそのまま再現する必要はないにしろ、それでもなにか、オリジナルのサウンドにあるなにか……そう、エネルギーとかフィーリングのようなものをステージで表現するのは、バンドとして不可欠だということなんだ。新メンバーを加えたのは、彼が僕たちの可能性を大きく広げてくれるからだよ。このアルバムを完成させたことによって、僕たちには新メンバーが必要となり、それでゴードンに加入してもらったんだ。彼は楽器をいくつも扱える、とてもいいミュージシャンでさ。これまで僕たちが加えたかったいろいろな要素を、ゴードンは補い、手を貸してくれる。だからバンド・サウンドは、よりよいものになったよ
——新作のタイトルをTHE WINTER OF MIXED DRINKSにした理由は? タイトルにあるウィンター(冬)やドリンク(酒)という言葉が、直接作品に関係しているわけではないんだ。このアルバムの大きなテーマは“海”になるわけで、でも、それをタイトルで言いたくなかったんだよね。タイトルではあまり海とは関係なく、アルバムに違った趣を与えてくれる言葉を使いたかった。酔っぱらった晩といったシチュエーションとかね。僕は曲の中で町の様子も表現しているから、タイトルでは町中にいても感じてしまう、孤独感のようなものを表現したかった。THE WINTER OF MIXED DRINKSは、人が自分を少々見失い、自分がどこに向かっているのかがわからなくなった瞬間のようなものでさ。そういった“さまよっている”感を出すには、“海”という言葉である必要はないよね。だから特に“海”を強調したくなかったんだ。それがこのタイトルの所以だよ
——このフレーズは、実際に10曲目の“Living In Colour”の歌詞に出てきますが、この曲とアルバム・タイトルとの関係は? 僕はいつも歌詞の一部をアルバム・タイトルに使いたいと思っており、そのセンテンスやフレーズは、ユニークでなければならない。そうすれば、その名前が出てきたらすぐに、“これはフライトゥンド・ラビットのアルバムだ!”ってわかるからね。この曲は、ある意味で、アルバムがどんどんアップビートになっていくターニング・ポイントになっている。このアルバムの中でポジティヴなクライマックスを作るナンバーだから、タイトルにはこの曲のフレーズを使うのが重要に思えた。もっとも、このレコードにはポジティヴなフィーリングがほかにもたくさん入っているけれどね。とにかく、THE WINTER OF MIXED DRINKSは、僕たちにとって大事なフレーズなんだ
——ところで、あなたは内臓に興味があるのでしょうか? たとえば“Living In Colour”には「Have my organs laid on ice〜」なんていう歌詞が出てきますし、前作、前々作のアートワークからも、ただならぬ臓器への興味がうかがえます。 うん、僕は解剖図が大好きなんだ。昔から興味があってね。体のイメージっていうのは、誰もが自分と関係づけられるものだよね。みんな臓器をもっているし、みんな肉体をもっている。肉体的な痛み、つまり気分が悪いとか、そういうのは、人の感覚の中でも非常に基本的なものだと思うんだ。だから、誰でも自分と関連づけられる。僕はそういうイメージを、自分たちの作品に使いたいんだ。そうすることで、僕たちの作品がファンにとってより身近で、共感できるものになればと思うよ。とにかく、僕は解剖図や臓器や体の部位にすごく興味をもっているんだ。けっして病的ではないけど、興味があるのは確かだよ
——スコットはアルバムのアートワークも手がけていますが、新作のジャケットにはどんな思いが込められているのでしょうか? 残念ながら、今回は内臓ではないようですが……。 今回は、デザイナーと一緒にジャケットを作ったんだけど、そのとき僕が持っていたイメージは、宗教やカルト絡みのものだったんだ。なにか意味があるように感じられる不思議な符号化されたイメージなわけだけど、おそらく最終的になんの意味もない。僕たちは偽の宗教やカルトのイメージを作り出そうとしたってわけ。だから今回は臓器はやめて、十字架やシンボルを使っているんだよ
——そんなさまざまな思いが込められた新作『THE WINTER OF MIXED DRINKS』が、日本では4月21日に発売されますが、バンドにとって、日本はこれまであまり縁のなかった国だと思います。日本にはどんなイメージを抱いていますか? 確かに日本は僕にとってあまり縁のない国だった。スコットランドに住んでいる日本人はすごく少ないから、接することは滅多にないし。でも、映画やテレビから受けたイメージでは、日本はすごく能率的な国で、文化的には東洋と西洋が不思議な混ざり方をしている気がする。あと、テクノロジーでも以前から注目されているよね
——今年はコーチェラをはじめとする大きなフェスティバルへ参加し、夏にはイギリス、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアでもツアーを行うようですが、日本でのライヴの予定は今のところないのでしょうか? 日本にはぜひ行きたいよ。行けたらいいのにと願っているんだけど、今はまだ可能性を探っているところなんだ。前からずっと、フライトゥンド・ラビットとして日本を訪れたいと思っていたから。日本のファンが、僕たちのライヴを見たいと思ってくれていたらうれしいし、今年の夏に日本に行くことができたら本当にいいな。僕たちにとって、夢の実現だからね
インタビュー:権田アスカ
通訳:豊田早苗